
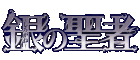
北斗の拳 トキ外伝 銀の聖者
| ストーリー | キャラクター | 流派・奥義 | ||


ストーリー紹介(7)
過去編
核戦争が起きる以前――― 身を呈してケンシロウを守り、流木をその背に受けたトキは、医務室へと運ばれていた。そんな兄に、ケンシロウは尋ねた。人を傷つけることを嫌う心優しきトキが、何故北斗神拳の学ぶことになったのかを。切欠は、ラオウに置いて行かれなくないという一心であった。そして拳を学ぶことを許された日、トキはラオウから言われた。もし俺が道を誤った時は、お前の手で俺の拳を封じてくれと。はじめは気にも留めていなかったその言葉は、月日が経つにつれ、今トキの背中に大きくのしかかってきていた。己に見合う強敵を求めるラオウにとって、今や北斗神拳は、その相手を制するための手段でしかなかった―――。 数年後、リュウケンが選んだ次期北斗神拳伝承者は、トキであった。トキ自身はその申し出を正式に受けたわけではなかったが、ケンシロウもジャギも、そしてラオウすらその決定に異論を挟もうとはしなかった。ラオウにとって、伝承者の座は野望ではなかった。彼の望む物、それはユリアという存在と、もう一つ。自らと対等の拳を持つ男、トキとの闘いであった。起こりうるはずがなかった二人の戦いが現実のものとなろうとしている。そのことを実感し、トキが夜空を見上げたその時―――彼の目は、北斗七星の脇に輝く小さな星を映していた。  己が死兆星を見たという現実を、トキは受け入れることが出来なかった。不安を掻き消す為、ユリアのもとを訪ねたトキは、己が誰かに縋ろうとしている臆病者である事を悟る。そしてその時、トキは理解した。己が伝承者に選ばれたことに、何故違和感を感じていたのか。それは、己が拳を極めたかったからではなく、兄に置いて行かれたくないという孤独に恐怖したがために拳を学んでいただけの人間だからである事を。そして各国の緊張がピークに達したその日、遂に核のボタンは押された。ケンとユリアと共にシェルターへと逃げる途中、トキは、再びあの死兆星を目にしていた―――。 己が死兆星を見たという現実を、トキは受け入れることが出来なかった。不安を掻き消す為、ユリアのもとを訪ねたトキは、己が誰かに縋ろうとしている臆病者である事を悟る。そしてその時、トキは理解した。己が伝承者に選ばれたことに、何故違和感を感じていたのか。それは、己が拳を極めたかったからではなく、兄に置いて行かれたくないという孤独に恐怖したがために拳を学んでいただけの人間だからである事を。そして各国の緊張がピークに達したその日、遂に核のボタンは押された。ケンとユリアと共にシェルターへと逃げる途中、トキは、再びあの死兆星を目にしていた―――。シェルターへ行くための昇降機は、既に人で溢れていた。乗ることが出来るのはあと二人―――。それは、トキにとっての転機であった。孤独を恐れ、兄を目指し続けた自分。しかしそれは、その場所から一歩も踏み出せていないという事でもあった。死兆星を見てしまった今、トキは自らの死を持って、兄への思いを断ち切ることを決めた。たとえ肉体は滅んでも、魂だけは大切な者達と共に生き続ける。それが、トキの選んだ孤独ではない死に方であった。二人を昇降機へと押し込み、死の灰を浴びたトキは、自らの命と引き換えに、心の繋がりという大事なものを手にしたのであった。 発病したトキに代わり、伝承者に選ばれたのはケンシロウであった。そしてそれは、北斗四兄弟の別れの時を意味していた。あくまで天を目指すというラオウに、トキは言った。あなたの拳を封じねばならない、と。トキにとって、今やラオウの背中は、あまりにも大きな存在へと変わっていた。しかしそれでもトキは、ラオウを超えなければならなかった。かつての約束を果たすため、そして、一人の漢としてそう望むが故に・・・ |

|
≪(6)幽閉編へ (8)再会編へ≫
